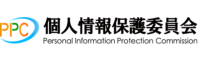個人情報保護制度
現代社会は、デジタル社会の進展に伴い、市民生活に多くの利便性をもたらしていますが、同時に、個人情報が大量に収集、蓄積され、流通することによって、プライバシーが侵害される危険性も高まっています。
平川市では、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づき、個人情報を適切に取り扱うことによって安心して信頼できる市政の推進を目指しています。
個人情報保護法の趣旨や概要、その対応などについては個人情報保護委員会ホームページをご参照ください。
市の保有する個人情報について
個人情報とは
個人情報
生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。
個人に関する情報とは、氏名、住所、生年月日のみならず、録音した音声、身体の特徴、メールアドレス等の、事実、判断、評価をできるすべての情報(防犯カメラの映像も含む)であり、暗号化の有無を問いません。
保有個人情報
平川市の職員が職務上作成し又は取得した個人情報で、平川市が組織的に利用するために保有しているものをいいます。
開示請求などの手続きについて
個人情報保護法では、自己を本人とする個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権が定められています。
平川市の保有個人情報について、どなたでも、自己の個人情報の開示を請求することができます。
手続きは、所定の請求書等に必要事項を記入し、情報公開担当窓口(総務課行政係)に提出していただきます。
本人確認をさせていただきますので、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の提示が必要です。
開示請求
開示請求を行う場合は、次の書類を提出してください。
平川市は、請求日から15日以内に開示・非開示等の決定を行い、請求者に通知します。
次の情報は、開示しないことがあります。
- 法令等の規定により本人に開示することができない情報
- 開示することにより本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれのある情報
- 開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報
- 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全の確保および秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 市や国等の内部又は相互間における審議、協議等に関する情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報
- 開示することにより市や国等が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
開示を決定した個人情報の閲覧・視聴は無料です。
ただし、写しの交付を請求された場合は、コピー代などの実費をいただきます。
訂正請求
開示請求により開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、訂正、追加又は削除を請求することができます。
平川市は、請求日から30日以内に訂正・非訂正等の決定を行い、請求者に通知します。
※訂正請求の手続きには、必要事項を記入した訂正請求書のほか、訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料を提出する必要があります。
利用停止請求
開示請求により開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。
平川市は、請求日から30日以内に利用停止・非停止等の決定を行い、請求者に通知します。
不服申立て
開示請求、訂正請求、および利用停止請求に対する平川市の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
個人情報に関する相談
個人情報保護委員会では、個人情報保護法に関する質問や、個人情報の取り扱いに関するトラブルの相談窓口として個人情報保護法相談ダイヤルを設置しています。
- 電話番号 03-6457-9849
- 受付時間 9時30分~17時30分(土日祝日および年末年始を除く)